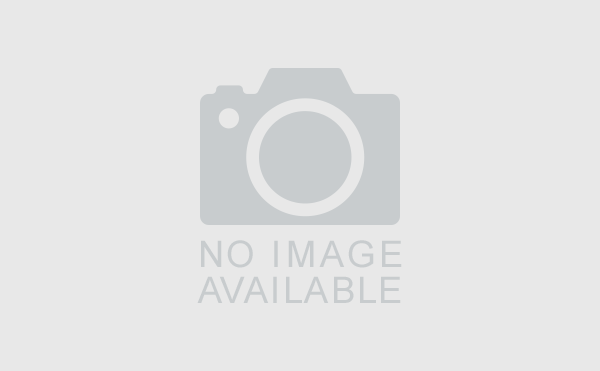買う前は毎週通うつもりだった。
焚き火もやる…
小屋も作る…
週末は野営だ…
地図にピンを打って自宅から購入山林の到着までの所要時間を何度も計算した。
道具は揃えたし、写真のフレームまで決めていた。
「自分の山」さえあれば生活は少し良くなる…そう思ってた。
山を買う前のイメージは多くの方が似ています。
小屋作りやブッシュクラフト、プライベートキャンプの貸切利用が日常になる…と想像される方は少なくありません。
検索でも「山を買う 毎週通う」「小屋作り 体験」「焚き火できる場所」といった言葉が多く使われており、理想の休日を求める関心の高さがうかがえます。
最初の3ヶ月は勢いがあるはずだった。
契約書にサインした夜、道具のチェックリストを書いた。
家族にも宣言した。
「今度の休日は山に行く」と。
所有すれば思いのままに使える。
管理も楽しみのうち。
そう決めていた。
本記事では、その「買う前の理想」と「3ヶ月後のリアル」の差分を具体的にお伝えします。
通う頻度…
移動時間…
維持管理の手間…
そして費用。
所有の現実を踏まえたうえで「まずは山林レンタルで試す」という選択肢についても整理します。
結論から申し上げると、買う前に“借りて確かめる”ことが、後悔を最小化する近道です。
読み進めていただければレンタル可能な山林見学予約までの流れもこのままご確認いただけます。
3ヶ月後の現実:山を買ったが毎週は通えなかった

予定と天候に負けた現実
最初の月は二度行った。
二ヶ月目は一度だけ。
三ヶ月目は天気と家庭の予定が重なってゼロだった。
「毎週通う」は想像の上では簡単だったが、現実では続かなかった。
所有するといつでも行けるはずなのに、実際には仕事の繁忙・家族の行事・雨風といった生活の要因が重なり、訪問頻度は落ちやすくなります。
回数が下がるほど「所有コストに対する体感価値」は薄れがちです。
山までの移動時間と積み下ろしの“往復コスト”
片道は90分前後。
往復で3時間。
荷物の積み下ろしに30分。
現地に着く頃には、やりたかった作業よりも休みたい気持ちが勝った。
山遊びはアクセスの負担がボディーブローのように効きます。
道具の積載・荷降ろし・帰路の疲労は次回の足を重くします。
結果として「来週でいいか」が積み重なり、理想の頻度から離れていきます。
維持管理に追われる週末
草は一週間で伸びる。
夏は一ヶ月で膝近くまで来る。
刈った…片づけた…倒木をどけた…気づけば夕方だった。
焚き火台は出した。
けれど火はつけなかった。
所有には定期メンテナンスが伴います。
草刈機の燃料・替刃、手袋や防護具、ゴミの持ち帰り、道具の乾燥と保管。
季節によっては蜂・蚊・マダニへの対策も必要です。
こうした作業は楽しい時間の前提でありつつも、週末の可処分時間を確実に削ります。
楽しむ時間< 管理の時間
「小屋を建てる」が目標だったのに「草を刈る」だけで一日が終わった。
やりたいことは前にあるのに、足元の雑草が先に片付けを迫ってくる。
理想は風景の中にあった。
現実は足元の雑草の中にあった。
体験の質は管理タスクの完了に依存します。
つまり“遊ぶための前提作業”がレジャー本体を圧迫し、満足度が伸びづらくなります。
ここで多くの所有者が「思っていたのと違う」というギャップに直面します。
想定外に増えるコスト
想定していたのは固定資産税と購入費だけだった。
実際は、草刈機・燃料・替刃・手工具・ブルーシート・ロープ・防虫用品が増えていった。
車の積載トレイも買った。
洗車の回数も増えた。
消耗は静かに積み上がった。
費用はお金だけではありません。
時間・体力・家族の理解・車両の摩耗といった“見えないコスト”も蓄積します。
利用回数が少ないのにコストが増えると所有の費用対効果は下がっていきます。
このように、山を購入した直後の三ヶ月で多くの方が「毎週通うつもりが続かなかった」という現実にぶつかります。
所有自体が誤りということではありませんが、限られた週末の中で“遊ぶ時間を最大化する方法”を選ぶことが大切です。
次の章では、所有に伴う見落としがちなコストと負担を整理しをご紹介します。
山を所有することの隠れたコスト

固定資産税と維持費・道具代は“静かに積み上がる”
最初は固定資産税だけ見て計算した。
大きな出費は一度きりだと踏んでいた。
実際は違った…
草刈機を買い、替刃を買い足し、燃料・工具・防護具・保管ラック・ブルーシート・ロープ…
季節が変わるたびに足りない物が出てきてレシートが増え続けた。
所有には購入費や税金以外に維持のための継続費が発生します。
とくに道具や消耗品は一度で揃いきらず、使用と季節に応じて追加購入が続くため、想定より総額が上振れしやすいのが実情です。
季節の整備(雑草・倒木・害虫)の現実
梅雨明けの一週で足首が隠れ、夏には草が一気に伸びた。
台風の後は枝が散らばり、倒木が道を塞いだ。
さらに蜂が巣を作り、ぬかるんだ路面にタイヤを取られた。
予定していた作業は、季節の“上書き”で何度もやり直しになった。
自然環境では季節変動が整備タスクを増やすため、雑草・蔓の繁茂、台風後の片付け、害虫対策、路面補修などが定期的に発生します。
これらは訪問頻度に関係なく進むため、行けない週でも“管理が遅れる不安”という心理的負担が残りやすくなります。
時間と体力のコスト
片道は90分ということは往復3時間。
荷物の積み下ろしでさらに30分。
現地に着く頃には、やりたかった作業よりも休みたい気持ちが勝つ日が増えた。
帰宅後は道具を乾かし、泥を落とし、また積めるように片付けた。
気づけば丸1日が終わっていた。
所有は移動・準備・撤収・アフターケアまで含めて時間を消費します。
可処分時間が前後作業に割かれるため、結果として「楽しむ時間<管理の時間」になりやすい構造であることをあらかじめ織り込む必要があります。
安全・家族・心理のコスト
斜面で足を取られた。
刈払機の振動で翌日は腕が上がらなかった。
雨雲レーダーを見て中止にした週末が続いた。
家では「また山?」と聞かれ、使えていない所有物がだんだんと心の負債に変わっていった。
山での作業は体力と安全管理が前提で、無理をしない判断が求められます。
加えて家族の理解や同意も継続的に必要となり、行かない週が続くほど“使えていない”ことへの心理的コストが積み上がります。
費用に表れにくいこれらの負担が満足度を下げる主要因になりがちです。
所有そのものは魅力的な選択ですが、以上のようなお金・時間・体力・心理のコストが重なると、当初思い描いた「遊ぶ時間」を確保しにくくなるのも事実です。
後悔を避けるためには、まず遊ぶ時間を最大化できる仕組みを選ぶことが大切です。
次の章では、その具体的な比較軸を整理していきます。
解決策としての「山林レンタル」
所有のデメリットを回避しつつ山の楽しみをそのままに、山購入3ヶ月後の現実で浮き彫りになったのは、維持管理と時間・体力の負担でした。
山林レンタルであれば、所有に伴う固定資産税や設備投資、定期整備の段取りといった重いタスクを避けながら、焚き火・ブッシュクラフト・野営などの体験はしっかり享受できます。
道具や整備を“全部自前”で抱え込まない分、週末の可処分時間を体験そのものに振り向けやすくなります。

年額7万円の“貸切”という安心
レンタルは年額7万円(税別)での貸切運用が可能です(山林により賃料は変わります)。
「人目を気にせず使える」「毎回場所取りをしない」というプライベート性は所有と同等の満足度を生みます。
初回はスタッフが安全ルールをご案内できる体制で、焚き火・刃物・火気の取り扱いといった不安も事前に解消しやすく、家族や仲間を誘いやすくなります。
“通える範囲で借りる”という現実的な設計
所有では立地を変えられませんが、レンタルなら自宅から60〜90分圏内など、生活リズムに合ったロケーションを選べます。
天候や家族の予定に合わせて負担の少ない距離を確保できるため、移動の往復コストが抑えられ、結果として通う頻度の維持につながります。
行きたいときに行ける距離感は、3ヶ月後の失速を避ける有効な打ち手です。
利用者は“遊ぶ”に集中できる環境
草刈り・倒木対応・害虫対策・路面整備などの定期メンテナンスは弊社が行います(オプション制)。
山林のメンテナンスを弊社に委託していただくだけで、メンテナンスの準備や片付けに追われて一日が終わるという状況を避けやすくなります。
所有で起こりがちな「楽しむ時間<管理の時間」の逆転を構造的に防げるのがレンタルの強みです。
まず借りて確かめる合理的プロセス
「山を買ったら毎週通うと思ってた…」という理想を実現できるかどうかは、生活サイクルとの相性で決まります。
いきなり所有を決めるのではなく、レンタルで3ヶ月から半年ほど運用してみることで、通える頻度・季節毎の使い方、家族の合意形成を現実ベースで検証できます。
合っていれば継続、さらに欲しくなったら所有を検討、という段階的な意思決定が可能です。
以上の通り、山林レンタルは所有のデメリットを避けつつ、3ヶ月後の失速を防ぎ“遊ぶ時間”を最大化する現実解となります。
“毎週通うと思ってた”理想をレンタルで現実に戻す
所有の現実とレンタルの合理性を踏まえたうえで、ここでは山林レンタルを選んだ週末が実際にどう変わるのかを具体的に描いていただきます。
目的はただ一つ、管理に追われず純粋に自然を楽しむ時間を取り戻すことです。

貸切の静けさで焚き火が主役に
到着して10分で火は起きた。
薪は乾いているし、風も読める。
もちろん隣のサイトなんて気にする必要はない。
炎の音だけに集中できる環境。
自分だけの山林だから今日は「準備に追われて日が暮れる」は起きない。
到着=体験開始。
このリズムが整うだけで週末の満足度は一段上がります。
人目を気にせず、時間も気にすることなく焚き火を楽しめることは、所有に匹敵する“自由度”をもたらします。
ブッシュクラフトは“少しずつの上達”が積み上がる
タープの角度を一度変える。
フェザースティックをもう一段細くする。
今日はここまで。
次は違う結びに挑戦する。
整備や路面補修に時間を取られない分、前回の続きに集中できます。
小さな上達が回数分だけ積み上がり、通うほどに「できることが増える」感覚を得ることができます。
安心して過ごせるプライベートキャンプ
子どもには火との距離感を教え、大人はコーヒーを淹れて癒される。
誰かが退屈しても、誰かは好きなことをしている。
楽しみ方は人それぞれで、この山林ではそれでいい。
貸切=プライベート空間だから、火気・刃物・エリア境界などのルールは初回に共有しておけば当日は確認だけで回ります。
気兼ねが減るほど会話が増え、体験の中心が「管理」から「時間の共有」に戻ります。

“通える範囲”だから半日でも満たされる
午前は山、午後は家。
往復3時間で疲れ切る週末はもう止めた。
さっと行って、しっかり満ちて、早く帰る。
自宅から60〜90分圏で自分だけの山林をレンタルできれば、移動の往復コストが体験を食い潰しません。
天候や家庭の予定に合わせて柔軟に組み替えられるため、通う頻度=満足度を安定して保ちやすくなります。
春夏秋冬の楽しみ方を“管理”から“利用”へ
春は新緑の匂いを吸い込む。
夏は夕立前の湿った気配を聞く。
秋は焚き火がごちそうになる。
冬は星と空気の透明さに息をのむ。
所有ではタスク化しがちな季節要因もレンタルなら体験のテーマに変わります。
季節が変わるたびに“整備予定”ではなく“利用計画”を立てられることが3ヶ月後の失速を防ぐ鍵になります。
以上のように、山林レンタルであれば管理に追われない週末を取り戻し「毎週通うと思ってた」理想を現実にできます。
「山を買う前にまずは借りてみる」という現実的な一歩
ここまでお読みいただき、タイトルにある「山を買ったら毎週通うと思ってた」という感覚が、決して珍しくないことをご理解いただけたはずです。
所有は魅力的である一方、固定費・整備・移動といった負担が積み上がると、楽しむ時間が削られがちです。
だからこそ、山を買う前に山林レンタルで“通える範囲”と“自分の週末”に本当に合うかを確かめていただくことをおすすめします。
見学はフォームからご希望日時をお送りいただき、日程調整のうえ現地でスタッフがエリア・安全ルール・利用方法をご案内する流れです。
まずは風や地形、アクセス時間、焚き火やブッシュクラフトのイメージをご自身の生活テンポに重ねてご確認ください。
フォーム送信→日程のご案内→現地見学→当日のご説明→ご検討、というシンプルな順序で進みます。
「山を買うか、そもそも山時間を諦めるか」の二択で迷う前にまずは借りて確かめる。
それが、後悔しないための最短ルートです。
山を買う夢を、まずは手軽に試す方法がここにあります。